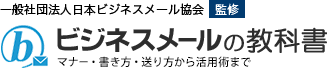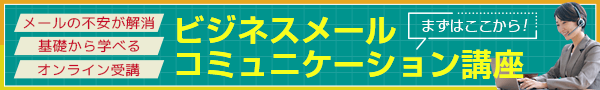転送するときも配慮が大切
「転送」は、受信・送信したメールを他のメールアドレスに送る機能
転送メールの件名には「forward」の略である「Fwd:」や「Fw:」の文字列が自動的に付きます。
ある程度メールを使い慣れている人であれば、件名を見ただけで「これは転送メールだな」と理解することができます。
転送だと分かれば、相手の意図を予測することも出来ます。
しかし、それだけでは、転送の経緯を知ることができません。
このメールがなぜ送られてきたのか、これを読んで自分はどうすればいいのか。
受け取った人が戸惑ってしまう場合もあります。
転送するときは前置きを
転送をするときは、冒頭に次のような前置きを入れるようにしましょう。
○○さんから頂いたメールです。
次回会議の参考になると思いますので、転送いたします。
前置きを読めば、メールを受け取った相手は、転送の経緯や、転送者の意図を知ることができます。
そして、あとに続く本文をスムーズに読み進めることができるのです。
編集・加工はルール違反
転送する文章は、編集・加工しない。
ビジネスメールでは、これが暗黙の了解となっています。
意図的に事実を歪めたりすると、あとあと辻褄が合わなくなることがあります。
メールの元々の差出人に迷惑がかかってしまうかもしれません。
メールは残るものです。
ルール違反の履歴も残りますから、あとで困るようなメールは送らないようにしましょう。
迷ったときは確認を
受信したメールを第三者に送っていいものかどうか、判断に悩むことがあるかもしれません。
そんなときは、差出人に確認を取りましょう。
頂いたメールを○○さんに転送しても差し支えないでしょうか?
このひと手間を惜しんだために、差出人との間に築かれた信頼が壊れてしまうこともあります。
それを立て直すのは容易なことではありません。
思い立ったらすぐ行動に移すことができるというメールのメリットを活かして、迷ったら差出人に確認しましょう。
スポンサーリンク