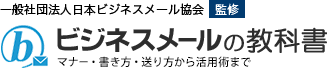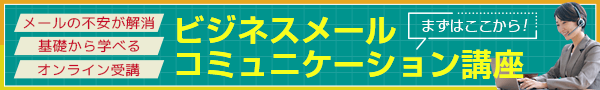電話ではなくメールで連絡をお願いしたい場合はどうすればいい?専門家が解説
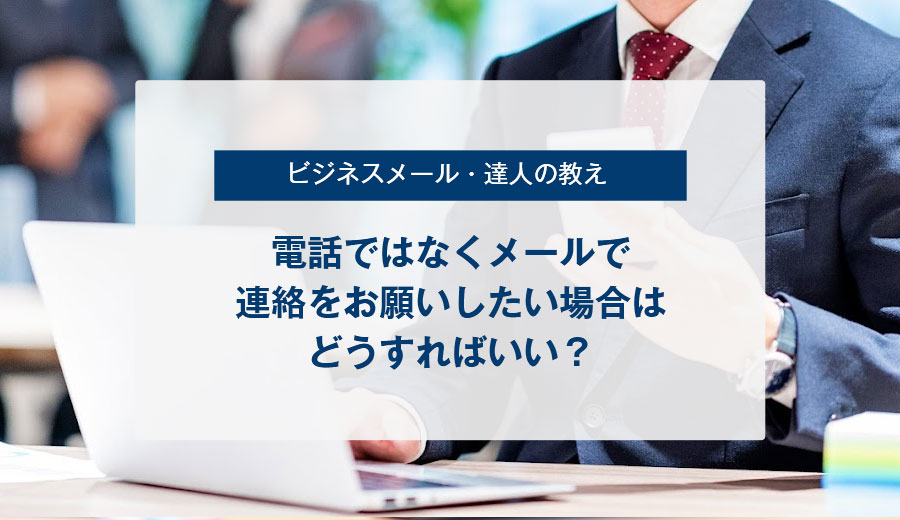
ビジネスメールの専門家が考える「電話ではなくメールで連絡をお願いする際の基本マナーと考え方」とは?
業務のデジタル化やテレワークの普及により、「電話ではなくメールで連絡してほしい」と感じる場面が増えています。とはいえ、いざメールでの連絡をお願いしようとすると、「失礼にならないだろうか」と不安に感じたり、戸惑ったりする人も多いのではないでしょうか。
この記事では、このような「電話ではなくメールで連絡をお願いしたい」という場合にどうすればよいかを、ビジネスメールの専門家が分かりやすく解説します。
目次
「電話ではなくメール」の依頼が必要になる主な状況とは
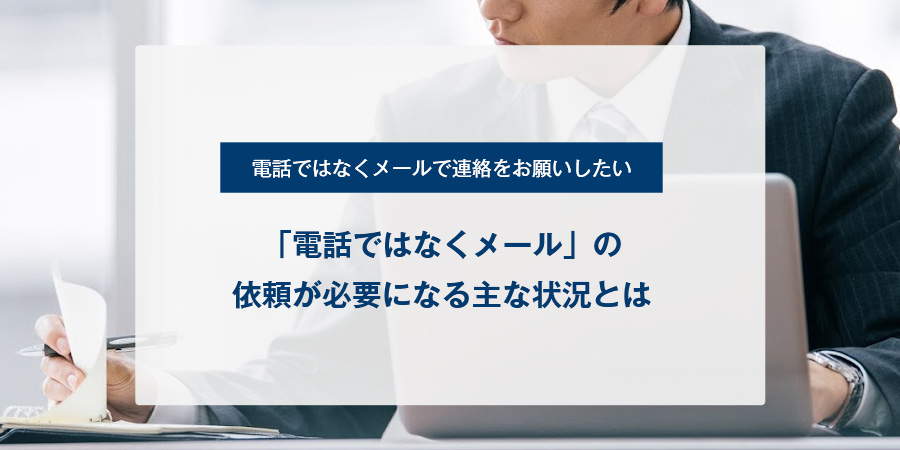
- 会議や商談などで電話に出られない時間が多いとき
- 記録を残す必要があるとき
- テレワーク中で業務時間が不規則なとき
- 相手の都合を気遣いたいとき
これらの状況は「相手とのコミュニケーションを円滑に保ちたい」という配慮から生まれる場合が多いようです。電話よりもメールにメリットを感じるからこそ「メールでお願いしたい」と考えるのでしょう。
電話よりメールを選ぶメリットと注意点
では、そのメールのメリットにはどんなことがあるでしょうか。電話には「早く伝わる」「確実に話せる」といった利点がある反面、「相手の時間を拘束してしまう」「話し忘れや聞き漏れが起きやすい」といったリスクを含んでもいます。
メールは、受け取った相手が自分の都合の良い時に読むことができるため、こちらの都合で時間を拘束せずに済みます。また、確認しながら行うことで書き漏らしを防ぎ、記録に残ることから後で振り返ることができます。
つまり、電話のデメリットを補うというメリットがメールにはあるのです。
関連記事
一方で、メールでの連絡をお願いする際には注意も必要です。「電話はやめてください」と一方的に伝えるのではなく、「お忙しい中恐縮ですが」「業務の都合上、メールでいただけますと幸いです」といった、相手に配慮した表現を心がけることがマナーです。
ビジネスで「電話ではなくメールでお願いします」を伝えるための正しい敬語表現とは?
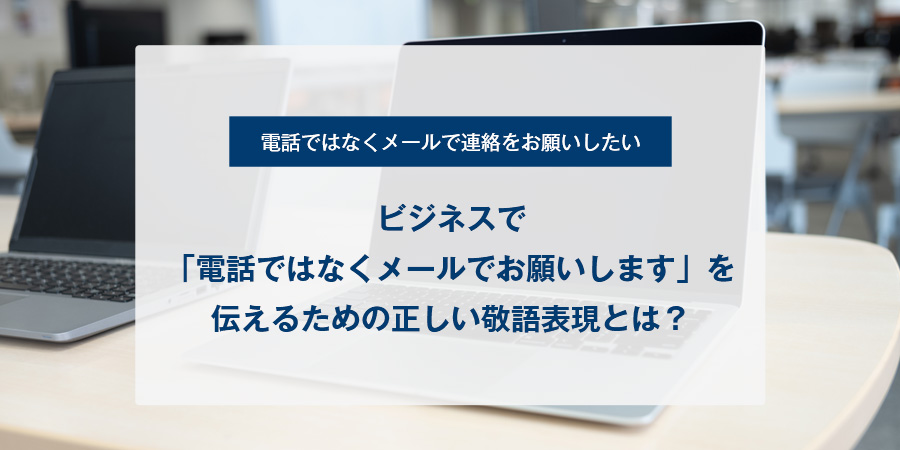
では、どのような点に注意すれば、失礼にならずに希望を伝えることができるでしょうか。
1.直接的になりすぎない柔らかい言い回し
「電話はやめてください」など断定的な言い回しを避けつつ、次のような表現を選びましょう。
- 「恐れ入りますが、メールにてご連絡いただけますと幸いです」
- 「お手数をおかけしますが、可能であればメールでご連絡いただけると助かります」
2.目上の人・取引先に使える丁寧な表現例
社外や目上の人に対しては、例えば次のようなより丁寧な言葉遣いが求められます。
- 「恐縮ではございますが、今後の連絡方法はメールを優先していただきたく存じます」
- 「業務の都合により、メールでのご連絡をお願いしております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。」
関連記事
3.社内・社外で言葉遣いを変えるポイント
対して社内であれば、次のようなカジュアルな表現も使えます。
- 「今月は打ち合わせが多いので、急ぎでなければメールでもらえると助かります」
「電話ではなくメール」をお願いするときの文例集
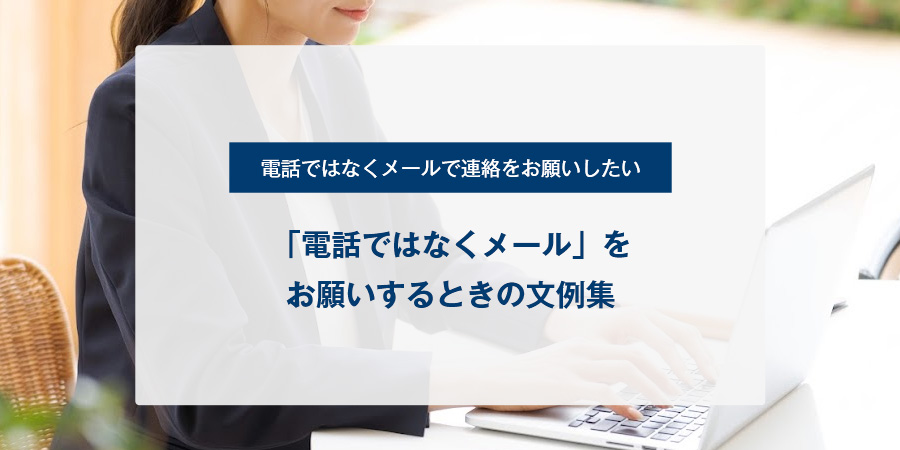
「電話ではなくメール」をお願いするメールの、具体的な場面ごとの文例を紹介します。
社内向け:業務効率化を意識した文例
今後の連絡方法についてのお願い
○○さん
いつもありがとうございます。
●●です。
最近、会議が続き電話に出られないことが多いため、
今後の連絡はできるだけメールでお願いできれば幸いです。
また急ぎの際は、チャットも活用してください。
どうぞよろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会
総務部 山田 太郎(YAMADA Taro)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-1 KIMURA BUILDING 5階
電話 03-5577-3210 / メール info@businessmail.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会 https://businessmail.or.jp/
アイ・コミュニケーション公式サイト https://www.sc-p.jp/
ビジネスメールの教科書 https://business-mail.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
取引先向け:失礼に聞こえない文例
ご連絡方法に関するお願い
○○様
いつも大変お世話になっております。
●●です。
業務の都合上、会議や外出が増えており
お電話に出られず、ご迷惑をおかけしております。
お手数ではありますが、
今後のご連絡を可能であればメールでいただけますと幸いです。
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会
総務部 山田 太郎(YAMADA Taro)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-1 KIMURA BUILDING 5階
電話 03-5577-3210 / メール info@businessmail.or.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本ビジネスメール協会 https://businessmail.or.jp/
アイ・コミュニケーション公式サイト https://www.sc-p.jp/
ビジネスメールの教科書 https://business-mail.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
英語メールでのフレーズ例
英語メールでは、次のようなフレーズが使えます。
- I would appreciate it if you could contact me via email instead of phone.
- Due to frequent meetings, I may not be able to answer phone calls. Email would be preferable.
「メールより電話がいい」という人への配慮と対応方法について
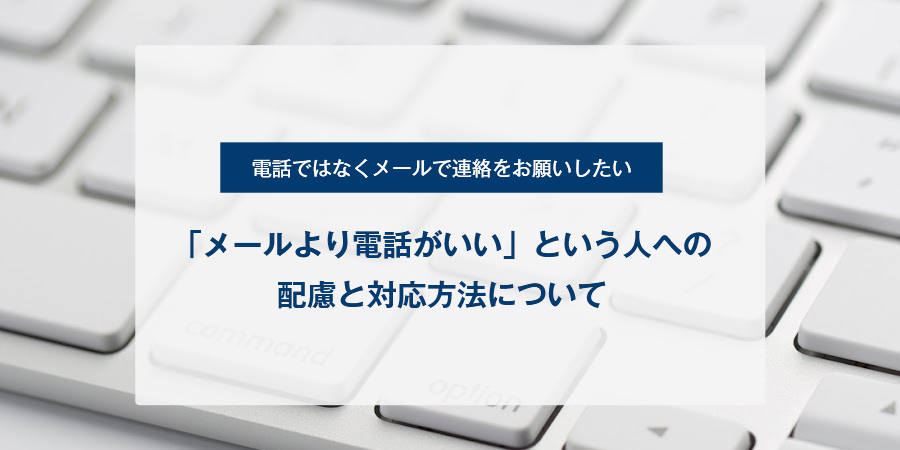
電話派の心理とその背景を尊重しましょう
「電話のほうが早い」「すぐに返答が得られる」などのメリットから、電話を好む人もいまだ少なくありません。特に、年配や現場の第一線で活躍している方の中には、メールよりも電話を好む傾向が見られるようです。
「相手の反応を見ながら話したい」「声のほうが微妙なニュアンスが伝わる」といった経験に基づく価値観が背景にあるのかもしれません。
こうした電話派の心理を無視して、「電話でなくメールで」と一方的に伝えるのは配慮に欠ける行動だといえます。相手に寄り添う姿勢を忘れず、「なぜメールを希望するのか」という理由を丁寧に説明することが大切です。
例えば、次のように具体的な事情を添えることで、納得してもらいやすくなるでしょう。
- 会議や打ち合わせが続き、電話に出られないことが多いため
- 業務上、記録を残す必要があるため
メール連絡の依頼を受け入れてもらいやすくするためにはフォローも重要
メールでの連絡をお願いした後、そのまま放置してしまっては、相手に不親切な印象を与えかねません。特に、これまで電話でスムーズに連絡を取り合っていた相手には、丁寧なフォローが欠かせません。
例えば、次のようにフォローの言葉を添えることで、「伝わっている」という安心感を与えることができます。
- ご連絡いただいた件、確かにメールで受け取りました
- お忙しい中、メールでのご対応ありがとうございます
また、メールでのやりとりがうまく進まなかった場合には、電話や別の方法に切り替えるなど柔軟な姿勢も重要です。大切なのは、自分の希望だけを通すことではなく、互いにストレスなく仕事を進められる状態を作ることです。
代替案(チャット・オンラインミーティング)を提案する方法
「メールが苦手」または「タイムラグ(時間のずれ)が気になる」という相手には、メールの代わりにチャットツールやオンラインミーティングを提案するのも一つの手です。
例えば、次のように伝えてみましょう。
- 「急ぎの場合はチャットでも構いません。そちらのほうがご都合がよろしければご連絡ください」
- 「必要に応じてオンラインミーティングも対応可能です。ご希望があればお知らせください」
このように複数の選択肢を提示することで、相手にとってもストレスが少なくなり、信頼関係の維持にもつながります。
電話とメールの使い分けルールを身に付けましょう
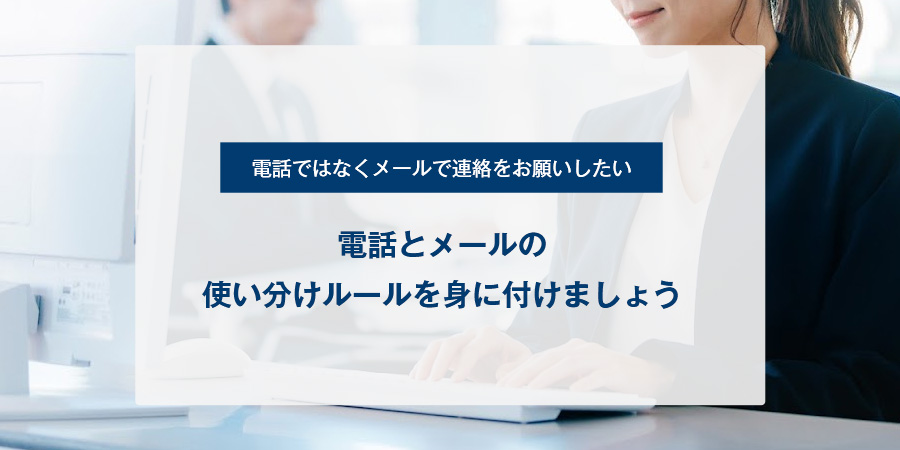
口頭が適しているケースと文字が適しているケース
コミュニケーション手段の選択は、目的と状況によって変わります。電話のような口頭によるコミュニケーションとメールのような文字によるコミュニケーション。それぞれが適しているのは次のようなケースです。
口頭(電話・会話)が適しているケース
- 内容が複雑で誤解が生じやすいとき
- 謝罪やお礼など感情を伝える必要があるとき
- 緊急対応が必要なとき
- その場で確認や判断を求めたいとき
文字(メール)が適しているケース
- 業務指示や契約関連など記録を残す必要があるとき
- 時間に縛られずにやり取りしたいとき
- 3人以上での情報共有が必要なとき
- 要点を整理して伝えたいとき
このように、口頭によるコミュニケーションと文字によるコミュニケーションは、どちらか一方が常に優れているというものではなく、目的や状況に応じて使い分ける柔軟性が求められます。
記録・証拠が必要な業務でのメールの活用方法とは
業務上のやりとりにおいて「言った、言わない」といった齟齬は、よくあるコミュニケーショントラブルの一つです。このようなトラブルを防ぐためにも、記録が残るメールの活用は極めて重要です。
特に以下のような内容においては、メールでのやりとりが適しているといえるでしょう。
- 契約や金額に関する話
- 業務の進捗報告
- 役割分担や納期の確認
- クレーム対応の記録
これらの内容は客観的な証拠として後で確認できることが求められるため、口頭ではなくメールなど文字によるやりとりが推奨されます。
急ぎの連絡でもメールを選ぶ場合の条件
「急ぎの要件だから電話を」という考え方が根強くある一方で、次の条件に合うような場合には、たとえ急ぎであってもメールの方が有効です。
- 相手が会議中や移動中で電話に出られない可能性が高いとき
- 連絡する内容に誤解が生じやすく、正確に伝える必要があるとき
- 相手が着信通知を設定しており、スマホでも見られることが分かっているとき
「取り急ぎご連絡まで」など急ぎの連絡であることを明示すれば、このような場合の効果的な連絡手段としてメールを活用することができます。
依頼時に避けたい失礼・誤解のもとになる表現とは?
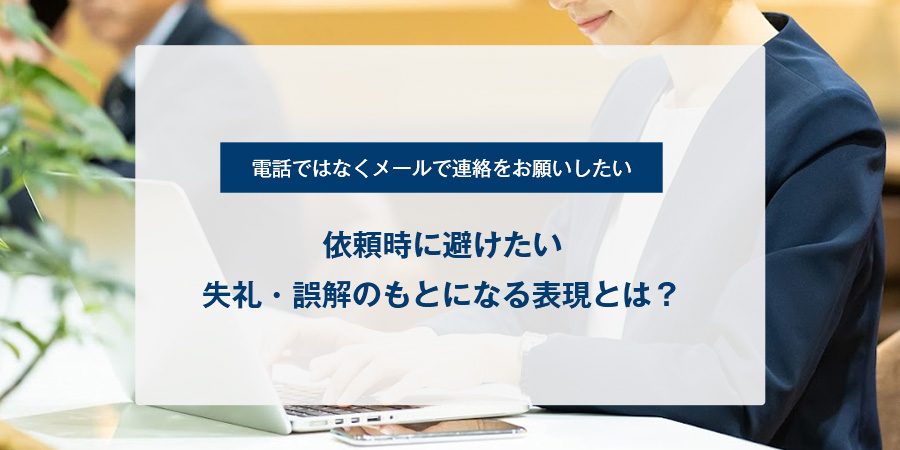
命令形・否定的ニュアンスを避けましょう
「電話はやめてください」「電話されると困ります」といった表現は、相手に強制や否定の印象を与えてしまい、関係を損ねる原因になりかねません。
依頼の表現では「お願いします」「ご配慮いただけますと幸いです」といった柔らかい語り口を、常に心がけましょう。
「メールで失礼します」などのクッション言葉の活用法
「メールにて失礼いたします」「取り急ぎメールにて連絡いたします」などのクッション言葉は、相手の気持ちを和らげる効果があり、メールの冒頭でよく使われます。
特に、電話の代わりにメールを送る場合には、このようなクッション言葉を添えるだけで印象が大きく変わります。
- 「ご連絡が遅くなり申し訳ございません。メールにて失礼いたします」
- 「本来ならお電話差し上げるところ、取り急ぎメールにて連絡いたします」
丁寧さと配慮を感じさせるこうした言い回しは、ビジネスメールにおける基本的なマナーの一つです。
誤送信や宛先ミスを防ぐためのチェック項目
メール送信前の「一呼吸」が、トラブルの防止につながります。次の項目をチェックして、誤送信や宛先ミスを防ぎましょう。
- 宛先(To/Cc/Bcc)に誤りがないか
- 件名と本文が一致しているか
- 敬称や表記の誤りがないか
- ファイルの添付忘れはないか
- 社外秘情報が含まれていないか
まとめ:電話ではなくメールでお願いする文化を職場に浸透させるには
「メールでお願いします」という文化を職場全体に浸透させるには、まず個人がその必要性とメリットを理解し、実践することです。業務効率を高める上でメールは極めて有効な手段です。
一方で、電話には即時性や感情伝達の強みがあります。大切なのは「どちらが優れているか」ではなく「どちらが適しているか」を判断する力です。
また、メール文化を定着させるには、社内でのルール作りや定期的な情報共有も重要です。この内容はメールで」「この件は電話で」という決め事を共有することで、無駄なストレスやミスを減らすことができます。
どちらか一方に偏らず、それぞれの利点を活かして電話とメールを柔軟に使い分ける。これこそが現代の働き方にふさわしいスマートなコミュニケーションスタイルです。
スポンサーリンク